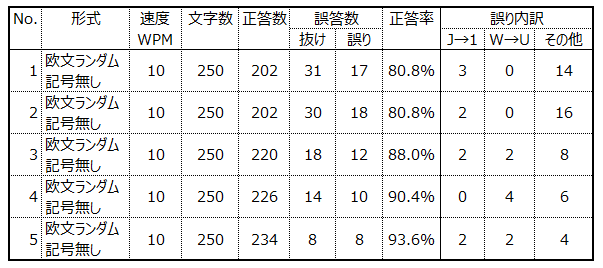少し前に「SD330のチューニングが面倒なので手抜きができたら良いな」ということを書きましたが、少しだけ検討を始めました。
以前はチューニングはそれほど面倒とは思っていませんでしたが、ATAS-120Aを使い始めてその便利さを知ることになり、とたんにSD330が不便に思えるようになったということです。
なるべく費用を掛けずにPCとリレーを使ってアンテナを制御できないかと考えています。リグとPCの間はCATコマンドを使い、周波数情報やSWR情報をリグから得て、それを元にPCがリレー制御するという方法です。なるべくTX ONはしたくないのでうまくNanoVNAが使えないかとも思いましたが、リグ周波数との連動がうまく行かなそうなことと、そもそもNanoVNAからどのようにデータを取ればよいかわからないため、次のように考えました。
① PC(JTDX)からリグに周波数指定(既存部分)
② リグからPCに周波数(変更)情報通知
③ PCでアンテナの伸縮方向と時間(所定時間)を計算
④ ③に従いPCがリレーON
⑤ ③の所定時間経過後、PCからリグに対して最低出力での送信を指示
⑥ リグからPCにSWR情報送出
⑦ 所定のSWR以下になったところでPCがリレーOFF
なお、元の周波数でチューニングが取れていない場合は③の計算自体できないため、一旦、アンテナを一杯に伸ばして(または縮ませて)それを基準点として伸縮時間を計算することになります。
空回りさせて良いのが最長点か最短点かは確認必要ですね。とは言え、マニュアルでチューニングしているときはそこはあまり気にしていないので、一杯まで行くとモータへの通電が自動で止まるのかも知れません。
また、最低出力であれSWRが高い状態でリグをTX ONできるのかどうかもわかりません。(ATAS-120Aではできていますね。)
それから、PC/リグ間、PC/リレー間のCOMポートをどうやって増やすか、PC/リグ間のCATコマンドはどうやってやり取りするか、PCから制御可能な適当なリレーがあるか、そもそもソフトはどの様に作れば良いか等、一から勉強すべきことが多過ぎて実現可能性は怪しいですが・・・
昔PCからモデムを制御するためATコマンドを出すのにPCの「ターミナルモード」というものを使った記憶があるので、手始めに「ターミナルモード」をネット検索したら「D-STAR」「IC-705」が出てきました。
先は長そうです。