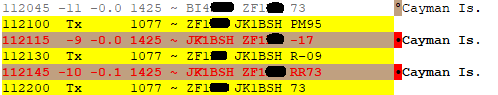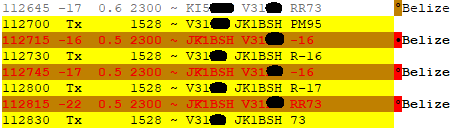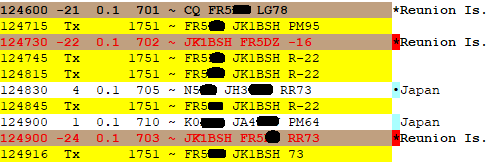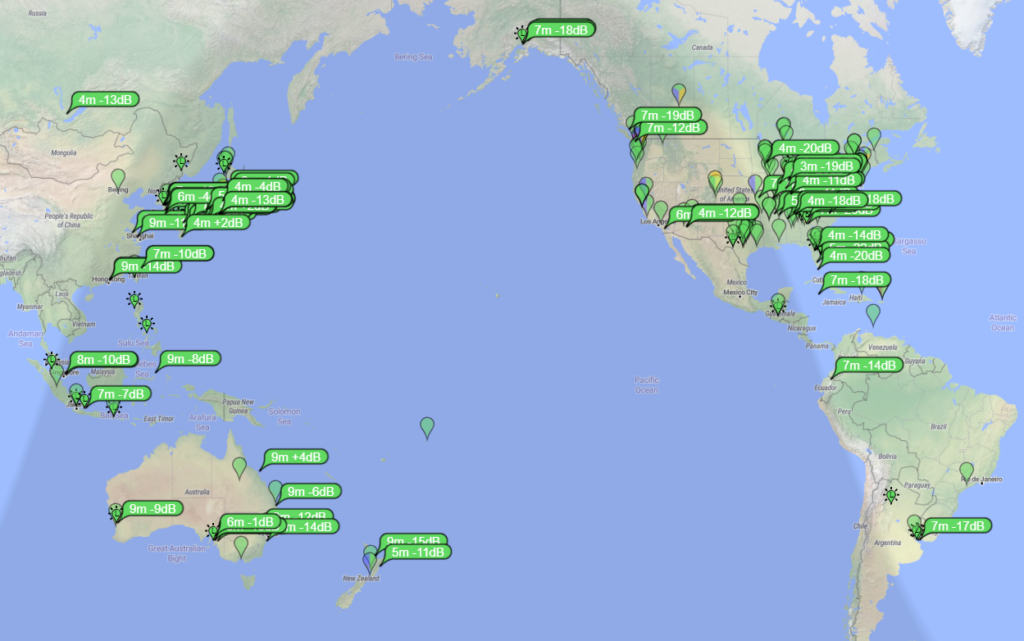先日、ロシア上空の飛行を避けるため欧州路線の一部でJALは「北回り」、ANAは「南回り」の運行を始めたとのニュースを目にしました。ただこの「北回り」「南回り」は昔のルートとは大きく異なるようですね。
私が昔ヨルダンに出張していたころは、北回りは会社の規則で役職が上の人しか利用できなかったため、JAL南回りで一旦アテネに出てそこから乗り換えることが多かったです。機材はDC10でした。当時は担当者でもエグゼクティブクラス(ビジネスクラス)を使うことができました。
この路線は給油のため途中3か所か4か所に寄港します。そのため成田からアテネまで20時間以上、丸一日かかりました。食事は4~5回は出たと思います。
当時のルートですが、成田を出るとまずバンコクに止まります。その後は曜日によって経由地が異なりカラチかデリーだったと思います。その先は更に複雑で、クウェートかバーレーンかジェッダに降り、カイロに寄る便もありました。ほとんどの空港で一旦降機しトランジットエリアで1時間ほど待機します。
しかし、ジェッダ(サウジアラビア)では、機内にとどまる必要がありました。着陸前には客室乗務員から「酒類は上の荷物棚にしまってください。」との注意喚起があります。サウジアラビアはとても厳格なイスラム教の国のため、酒類の持ち込みは禁止で、たとえ入国せずにトランジットでもNGでした。着陸してしばらくすると係官が乗り込んできて、通路を歩きながら一通り目視チェックします。荷物棚まで開けることはありませんでしたが、酒類を持ち込んでいることはおそらく承知しているのでしょう。形式的なチェックでした。
カイロ寄港便ですと更に遠回りになりますので、成田からアテネまで24時間近くかかったと記憶しています。
アテネに到着するのは夜で、そこで一泊して翌日アンマンに向かうので、往路だけで足掛け3日の旅になってしまいます。帰国時はバンコクまで戻って来ると同じアジアということもあって、何か日本に帰ってきたような錯覚を覚えたものです。
また、スーダンの出張では、アフリカの場合は担当者でも北回り便の利用が認められていましたので、北回りでパリに出てそこから乗り継いでいました。ヨーロッパまではノンストップではありませんでしたが、南回りとは違い、寄港地はアンカレジかモスクワの一か所だけでした。
アンカレジのトランジットエリアには立ち食いそば屋があって、現地の日系のおばさんたちが日本語で迎えてくれます。やはりバンコクと同じように、帰国便でここに立ち寄るとホッとします。
と、「北回り」「南回り」という言葉に反応して無線とは全く関係の無い昔話を長々と書いてしまいました。今では飛行機の燃費が向上し航法技術も格段に進化していると思いますので、少し遠回りしても途中で一旦降りるということも無いのでしょうね。