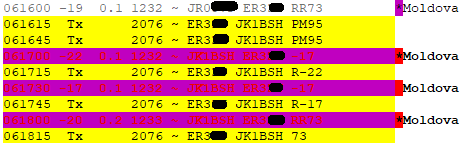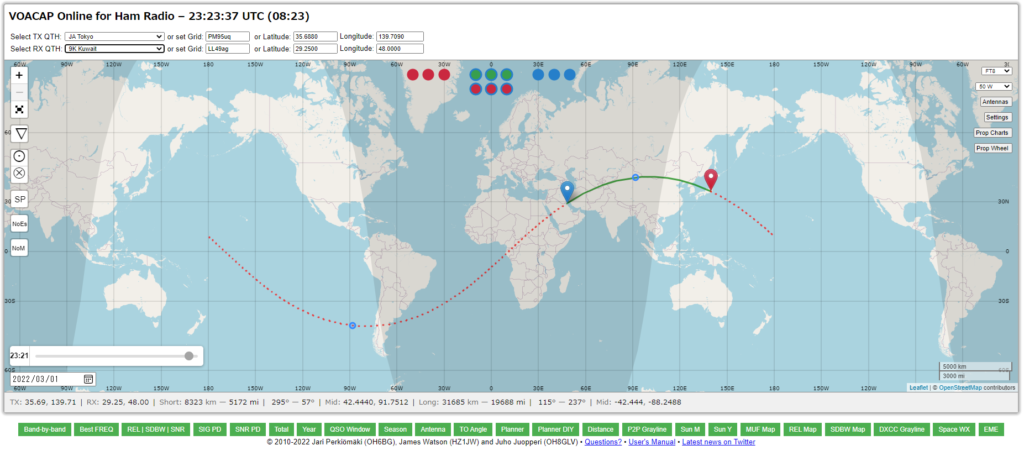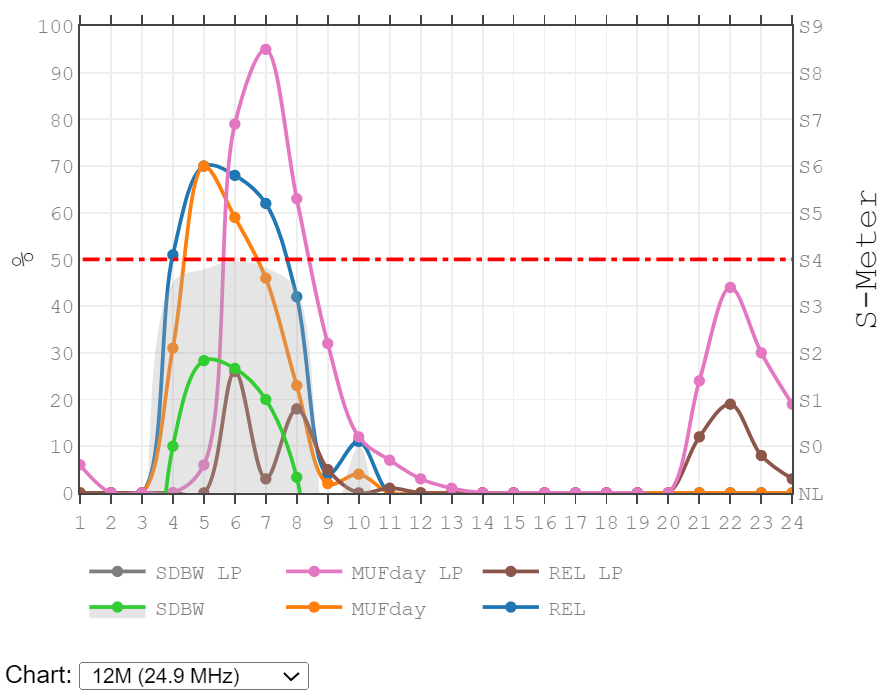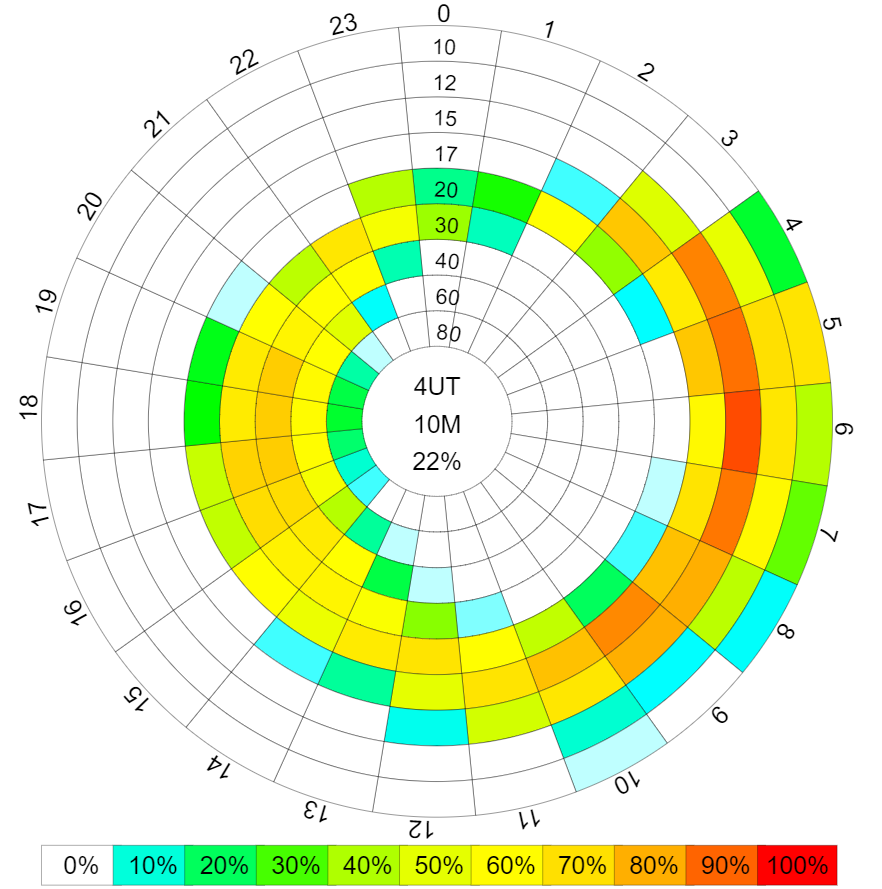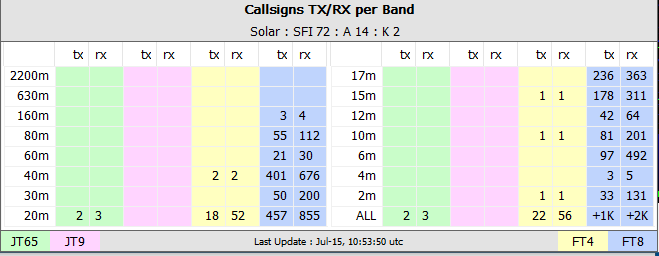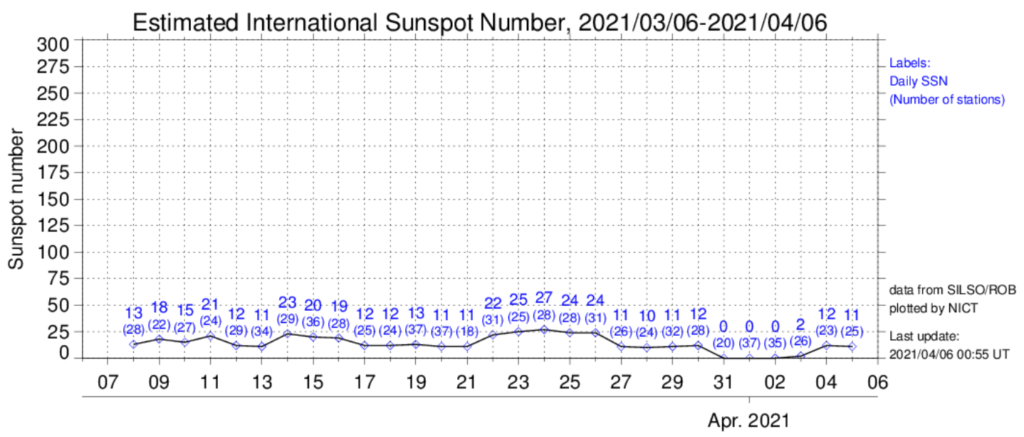無線機器の電波を一定時間で人体がどれほど吸収するのかを示す指標としてSAR(Specific Absorption Rate:電波の比吸収率)があります。
携帯電話機では、SARについて頭部組織10gに吸収されるエネルギー量の6分間平均値が2W/kgを超えないよう義務付けられており、各通信事業者は機種毎にSAR値を公表しています。
例)NTTドコモの関連サイト
他方、アマチュア無線機にはSARの基準は無いようです。
そこでFT3DにSRH770アンテナを付けてヘッドセット無しで5W運用したときの頭部への影響を探ろうと、ネット情報などを参考にしてSARを推定してみました。携帯電話機でOKとされている2W/Kg以下になっていればひとまず安心だろうということで・・・
下に挙げた諸々の資料によると、一般環境における「電磁界強度指針(6分間平均値)」は、電力密度S(mW/㎠)が30MHz~300MHzでは0.2、300MHz~1.5GHzではf/1500とのことです。
また、アンテナと人体との距離が近い場合は「局所吸収指針」としてSARを使い、100KHz以上300MHz未満で20cm以内、300MHz以上6GHz未満(※)で10cm以内に適用され、それ以外の距離においては電磁界強度指針によります。(※過去の資料では3GHz未満となっていますが、最近の資料によると6GHz未満までは局所吸収指針が整備され6GHz以上は未整備で、5G通信のミリ波運用に備えて検討中のようです。)
SAR自体は電波暗室の中で実機とファントム(疑似人体)を使って実測しないと出てきませんので、まずは簡易的に理論上の電力密度を求めてみます。
電力密度(W/㎡)=(電力xアンテナゲイン)/4πd2
(その他パラメータは考慮していません)
ここでFT3Dの送信出力(5W)、SRH770のアンテナゲイン(430MHz帯で5.5dBi=3.5倍)、距離d(0.1m)を当てはめてみると・・・
電力密度=141W/㎡=14mW/㎠
430MHzにおける電磁界強度指針は430/1500=0.29mW/㎠ですから、約49倍とかなり大きな値になりました。
なお10cmの距離では局所吸収指針が適用されますので、電力密度(mW/㎠)をSAR(W/Kg)に換算する必要があります。頭部組織の電波吸収特性は完全に無視するとして、仮に60Kgの人の投影面積を0.6㎡とし、頭部の重さと投影面積をその1/10にした場合・・・
・頭部の重さ:6Kg
・頭部の投影面積:0.06㎡
より、頭部における電波吸収率(?)SAR(W/kg)は
SAR=電力密度 141W/㎡ x 頭部投影面積 0.06㎡ / 頭部の重さ 6Kg = 1.41 W/Kg
で、2よりも小さくなりました。減衰パラメータやアンテナエレメント長は考慮していませんので実際はこれよりも低い値になるものと思いますが、逆に真のSARは頭部組織の電波吸収特性によるところが大きいと思われますので、これを無視して「SARを導き出せた」というのは無理がありますね。
一方、電磁界強度指針との関係では、指針の0.29mW/㎠以内に抑えるには70cmほど離す必要がありそうです。ちなみに2mバンドではSRH770のアンテナゲインは2.15dBiですので、430MHzでOKであれば2mでも問題無いと思われます。
この様にかなり雑な考察ではありますが、一応携帯電話機のSAR基準値以下の値が出たものの電磁界強度指針からは大きく外れていますので、「FT3D+SRH770」の組み合わせでヘッドセット無しの5W運用はできれば避けた方が良いかも知れません。今後、このリグで本格運用するときは「SSM-BT10」が活躍しそうです。
ちなみにFT3D標準添付のホイップアンテナのゲインはわかりませんが、5W出力の場合、仮にアンテナゲインを2.15dBiとすると電磁界強度指針以下に抑えるためには50㎝弱、アンテナゲインを0dBi(-2.15dBd)とすると40㎝弱、人体から離す必要がありますね。
(参考資料)
ARIB「くらしの中の電波」
総務書「電波防護のための基準の制度化」
総務省「電波防護のための基準への適合確認の手引き」
総務省「局所吸収指針の概要について」
総務省「電波の安全性に関する調査及び評価技術」のページ
電波防護指針(H9/4/24付)