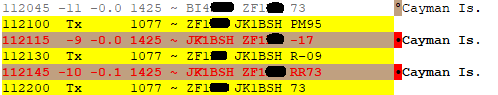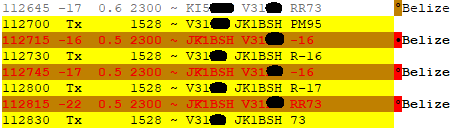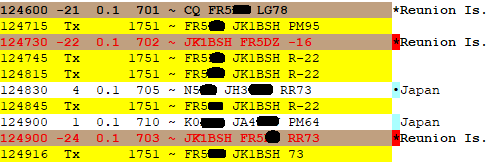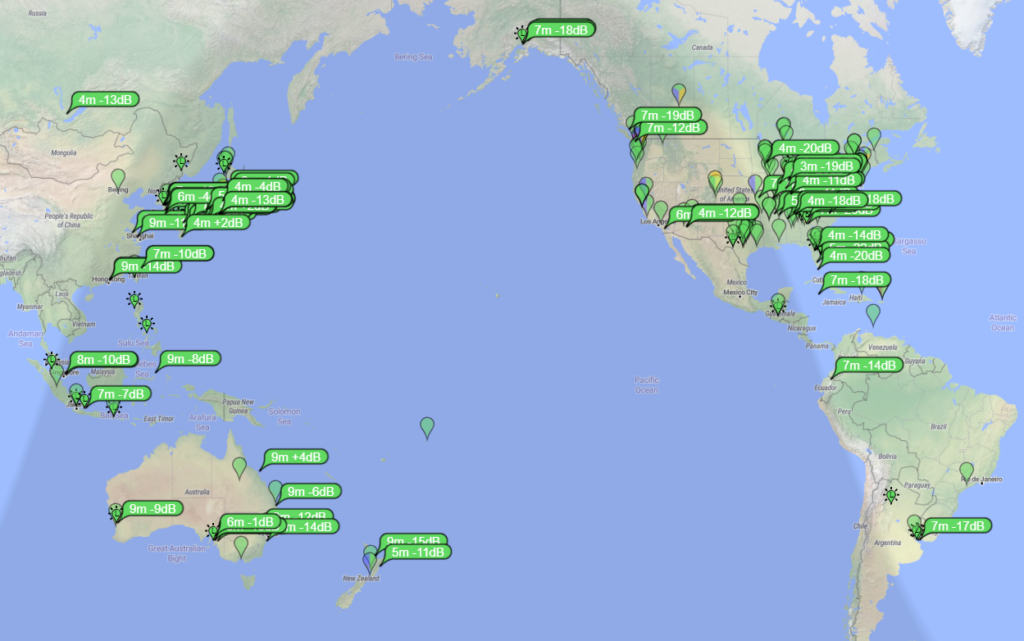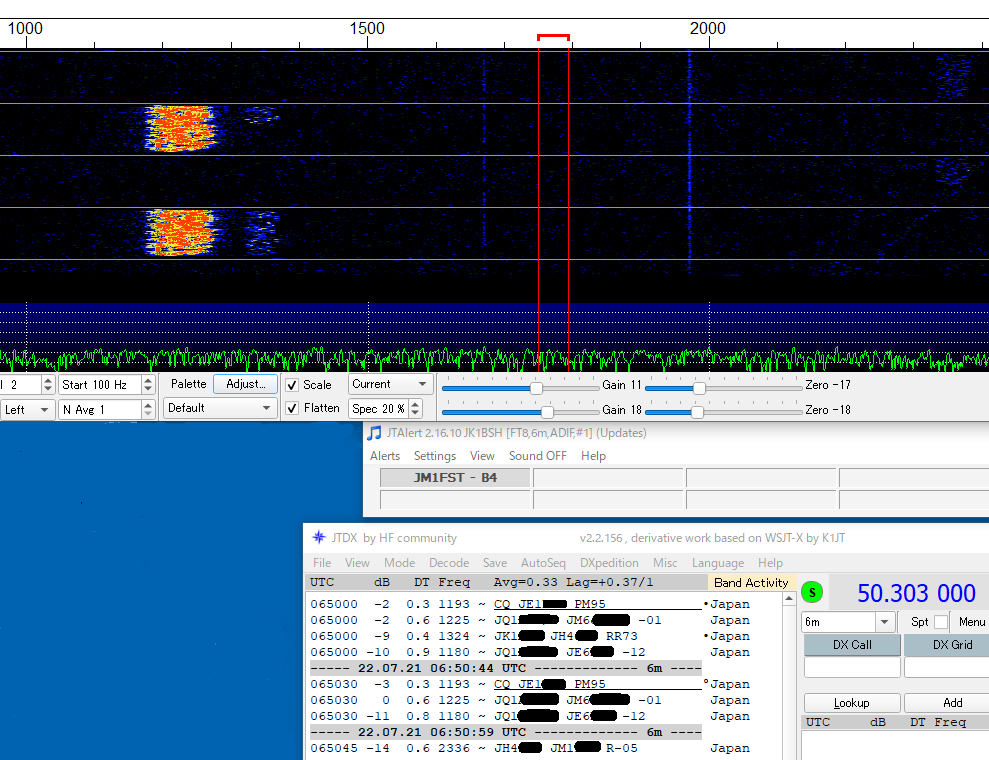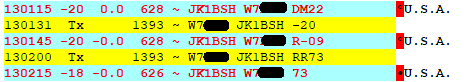無線以外の趣味の話の続きとして、今日はキャンピングカーについて書きます。
トラックのシャーシにFRP製のシェルを架装した、いわゆる「キャブコン」と呼ばれるタイプに乗っていました。長さは5m、幅は2m強で何とか普通車用の駐車場に収まるサイズですが、高さが突起部含めて3m近くあるため立体駐車場に入れることはできません。

装備はシンク、2口コンロ、電子レンジ、DC/AC/LPGで作動する3way 冷蔵庫、カセットトイレ、シャワー、FFヒーター、サイドオーニングなど一通り備わっており、清水タンク、グレータンクはそれぞれ90L程度の大きめなもの、また今では珍しいガス温水器も付いていてお湯も使えました。5KgのLPGボンベを積んでいるのでそれほど頻繁にガスを充填する必要はありませんでした。ナビとTV、あとは後述のルーフエアコンを後付けしました。
電源は100Ahのサブバッテリが2ヶと1500Wインバータが付いていましたので1 昼夜はそれで賄うことができ、外部ACからの充電や走行充電も可能です。
ベッドはバンクベットとダイネットを展開したベッドを使い、家族、ワンコ共々快適に過ごすことができました。
唯一不満な点は、駐車中でも使えるエアコンが付いていないことでした。夏は高地で過ごす分には涼しくて気持ち良いのですが、暑くて湿気が多い場所では結構宿泊が厳しかったため、Coleman製のルーフエアコンを後付けしました。これはアメリカ仕様で110Vタイプのため一旦トランスで昇圧して使っていましたが、起動時の突入電流が大きいため、オートキャンプ場のAC電源では場所によってはブレーカが落ちたりして使えないこともありました。
最近のキャンピングカーは家庭用の省電力エアコンを使っているものが多いようですので、この様な問題は起きにくいと思います。昔の国産キャンピングカーは、アメリカ車やヨーロッパ車の仕様や部品を流用したものが多かったため設備も豪華だったのですが、逆にオートキャンプ場やRVパークなどのインフラがあまり整備されておらず、今から思うと少々持て余し気味だったと思います。
しかし家を出てクルマに乗り込めばそこはもう別荘ですので、思い立ったらすぐに出発ということもしょっちゅうでした。何と言っても宿の心配をする必要がないのは気楽で良いですね。高速道路のSAやPAも当時は「仮眠限定」とは謳っていませんでしたし・・・ 結局5年間ほど乗っていました。
ボートにせよキャンピングカーにせよ架装設備のメンテは自分で行う部分が多く、また洗艇・洗車も結構面倒で、操縦や運転も気を遣うため、若いうちは良いのですがこの歳になるとさすがに運用(?)は難しいかなと感じます。若いうちに色々と体験して楽しむことができて本当に良かったと思っています。
やはり「定年後に時間ができたらのんびり」楽しむにはアマチュア無線が最適ですね。