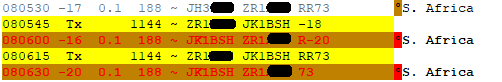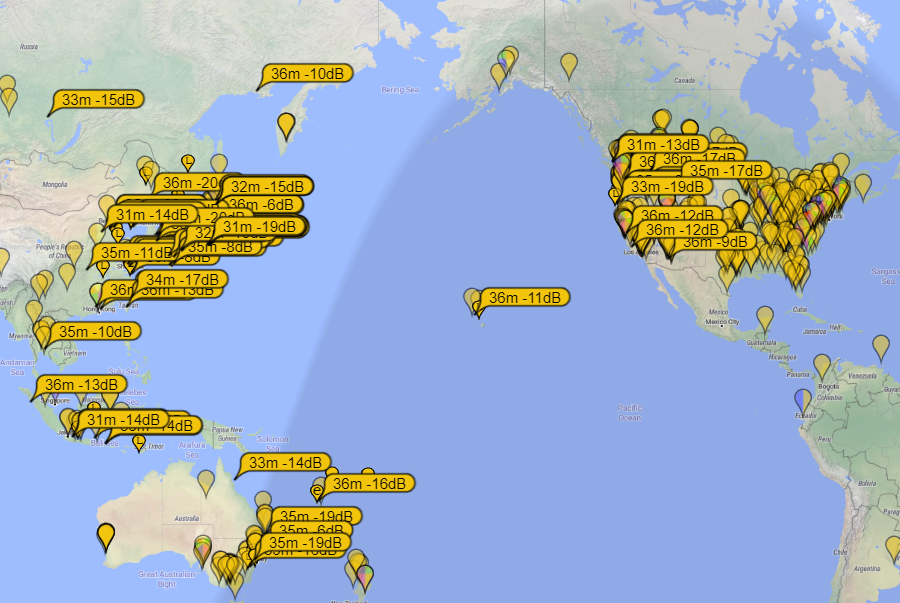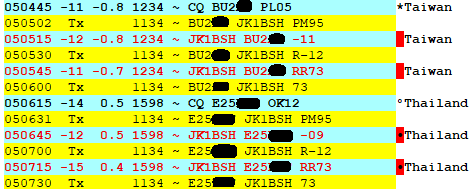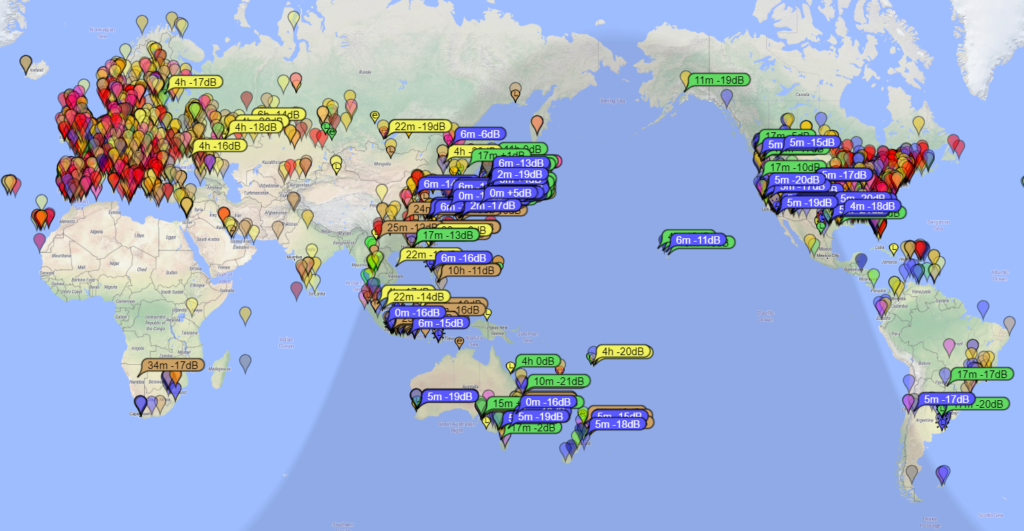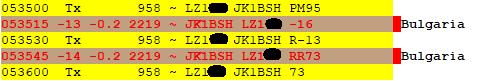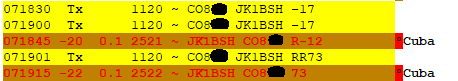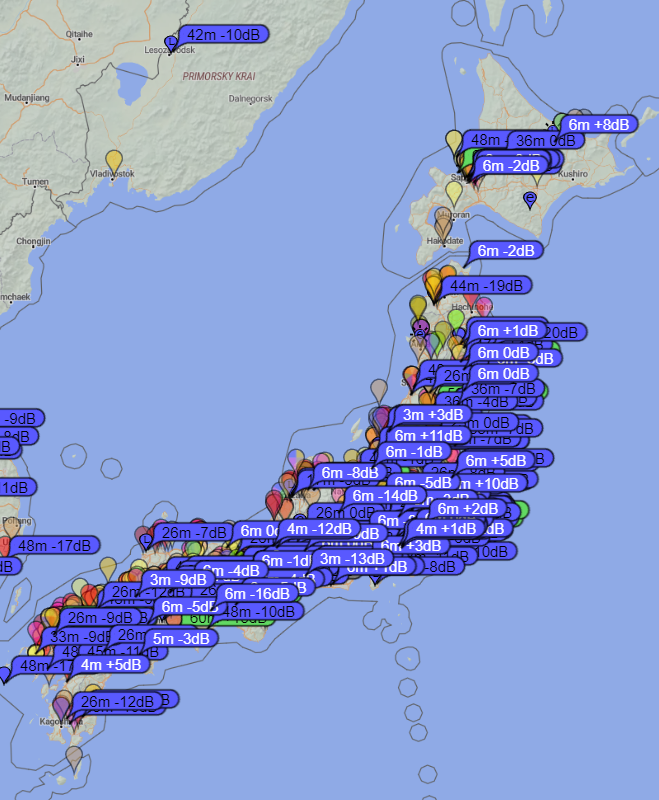先週、無線以外の趣味について触れましたが、その中でボートに関してもう少し詳しく書いてみたいと思います。
かつて所有していたのは米国ベイライナー社のシエラ2255という中古のインアウト艇で、全長7m弱のコンパクトなボートながら前方のバウバースにはソファ・テーブル付キャビン、トイレ、シンク、冷蔵庫、電気コンロが付いていて、操縦席の下にはミッドバースとして大人2人が並んで寝られる床スペースがあり、また清水タンクのほかブラックタンクも装備されていましたので、国産艇のようにマリーナ内で垂れ流すことなく快適に過ごすことができました。
上部の操縦席があるキャビンは基本はオープンですが、四方を透明ビニール付の幌で覆うことでサンルームにもでき、寒い時期でも快適です。

このマリーナは海上係留が基本なので船中泊ができます。ポンツーン(浮き桟橋)に設置された陸電AC100Vのポートや水道も自由に使えましたので特に不自由は感じませんでしたが、エアコンが無かったため夏の暑い時期の宿泊には少し厳しいものがありました。
別荘のような感じでもあり、またキャンピングカーでオートキャンプ場に宿泊するような感じでもあります。
昼間は、風や波の具合にもよりますが気の向くまま船を出してゆったりと過ごしました。船を出すのはブラックタンクの中身を空にする目的もあります。大きな船ではないため外洋は航行できませんが、逆に川や運河は通航可能でしたので普段とは違う景色を楽しむことができました。
ところで、この「インアウト艇」というのは、エンジンが船内に設置されギアやプロペラが船外ユニットに収められたボートのことを言います。一方、国産の小型プレジャーボートは、エンジン付き船外機がほとんどかと思います。インアウト艇は、エンジンのメンテがし易い反面、船外機艇と異なり停泊中に船外ユニットを上げても十分に水面から出ないため、漏水によるギア腐食のリスクがあり定期的なオーバーホールが必要です。
また海上係留と陸上保管を比べると、海上係留の場合は塗料によってはすぐに船底がフジツボなどで覆われますのでたまに陸揚げして船底掃除をする必要がありますし、係留費用も高くなります。今日の様に台風が近づいているときは、マリーナスタッフの見回りはあるものの、基本的には自分で係留ロープの確認や張り直しなどが必要です。
一方、陸上保管の場合は船中泊ができないことと、船の上げ下げに時間がかかるという不便さがある反面、船体の痛みが進みにくい、悪天候でも安心できる、保管費用が比較的安い等のメリットがありますので、使用目的や使用頻度、予算などで決めることになるかと思います。一般的にはマリーナステイ目的では海上係留、釣りなどの目的で使う場合は陸上保管というイメージです。
ちなみにこの船を所有していたのは20年ほど前になりますが、当時8年落ちの中古艇を、クルマでいうと標準的な国産大衆車が1台買えるほどの価格で購入し、1年半ほど楽しんで同じ店に半額で引き取って貰いました。
経済的にどうかは別として、その間の体験は家族にとっても大きな価値があったと思っています。