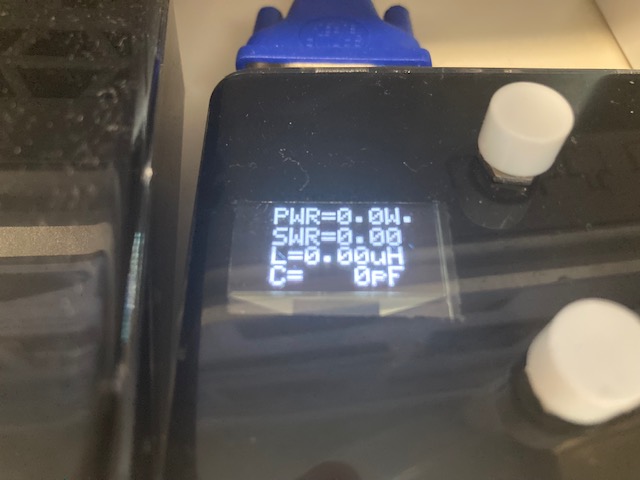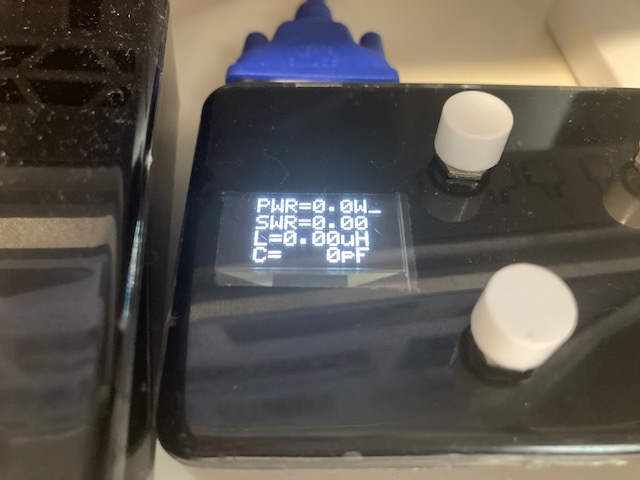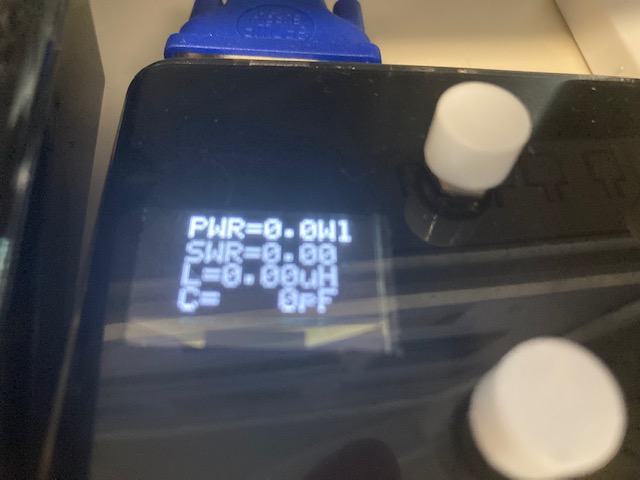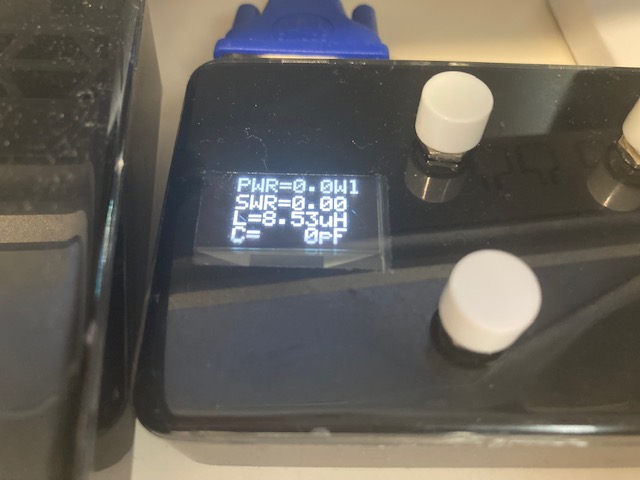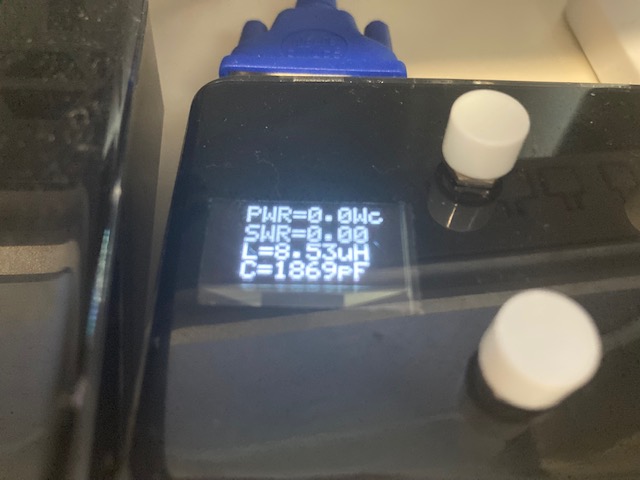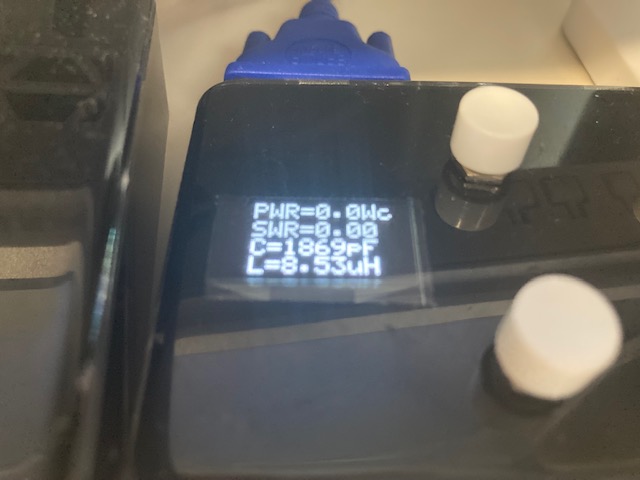真剣にFC-40を検討している中で、標準添付品のコントロールケーブルの長さが5mしかないことが気になっています。当局の場合は、シャックの隣がすぐベランダとは言え、引き回しを考えると5mでは足りないことは明らかです。
もっとも専門店には10mを初めとして5m刻みで30mまでのケーブルも用意されているのですが、10m長のものでも1万円を超え、目玉が飛び出しかねない価格です。
そこで、FC-40を使用されている方のブログや他に代替品が無いかネットで調べてみました。
まずはコネクタの仕様ですが、ミニDIN 8ピンのオスがケーブルの両端についていることが分かりました。コネクタ単体はあまり流通していないようですが、マル信無線電機さんの「ミニDINプラグ 8P(MP-371/8)」というのがありました。価格は税込みで1ヶ400円ちょっとです。延長ケーブルを作る場合はメス側も必要で、これは「ミニDIN中継ジャック8P(MJ-372/8)」だと思います。税込み250円弱ですね。
ネットの写真で見ると、DINとミニDINでは大きさは違うものの全体の形状がよく似ているため間違えそうですが、見た目、明らかに接続ピンの太さが違います。
一方、8芯ケーブルは色々ありそうですが、私は半田付けが下手なこととシールドをどこにつなげれば良いかも分からないので、コネクタ付きの既製ケーブルを探すことにしました。
Amazonで調べたところ、「サンワサプライ キーボード延長ケーブル 3m KB-K98-3K」という3m長のストレートケーブルを見つけました。コネクタは、ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメスとなっています。これはPC-9821のキーボードケーブルを延長するためのケーブルとのことです。PC-9821(PC-9800シリーズ)本体は、とうの昔にディスコンになっていますが、保守部品は未だに需要があるのですね。価格は1本あたり税込み1,500円弱でした。
もし10mの長さが必要な場合は、この延長ケーブルを2本(6m分)使えばかなりお得ですね。ちなみにこのケーブルをFC-40の延長ケーブル用として購入された方のレビューが載っており、特に問題なく使用されているとのことです。
なお、このケーブルはそもそも屋内用ですのでリグ側にこれを使い、屋外のATU側には付属の5mケーブルを使うのが良いのでは・・・と思っています。屋外側に長さが必要な場合は延長ケーブルを何本も使うのではなく、所定の長さのケーブルに交換した方が良いかも知れません。
ということで、コントロールケーブル長の問題は何とか解決できそうです。ところで肝心のFC-40ですが、各ネットショップでは「予約」や「納期未定」などと表示されていて、品薄状態のようです。