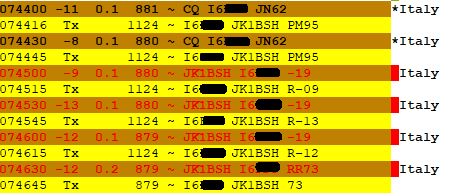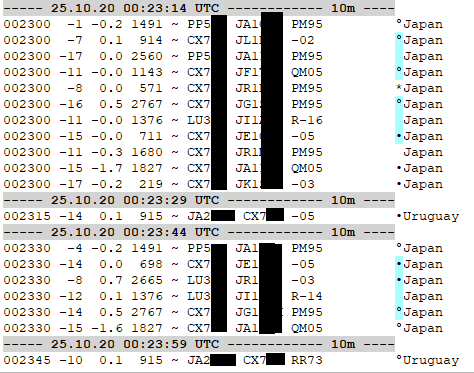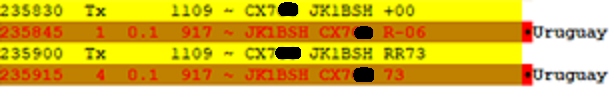懐古的な内容になってしまいますが、私の無線との関わりは小学校時代に遡ります。
電波を発信する機器(=送信機)との付き合いとしては、おもちゃのトランシーバー(学研ラジホーン)で遊んだのを皮切りに、ラジコン戦車を作って走らせたりしたことがありました。当時、ラジコンには簡易型の「シングル方式」というのがあり、これは送信機のボタンを押していくとサーボモータが動いて、前進、右、左、停止、後進など、順序は忘れましたが順番に切り替わっていくものでした。
ヒノデ製のラジコン装置で、水色の送信機の筐体には電源用のスライドスイッチとコントロール用の赤い押しボタンスイッチがついていました。送信機と受信機、サーボモータがセットになって価格は1万円ほどだったと記憶しています。
また、ヒノデのシングル方式の送信機は2種類あって私が使っていたのは安い方ですが、高い方はシングル方式ながらも高級感があり金属筐体にメーターがついていたように思います。本当はこちらの方が欲しかったのですが言い出せませんでした。変なところで親に遠慮したのかも知れません。
ラジコン装置を搭載する戦車はタミヤ製 1/25スケールの「パンサー」でドイツの代表的な戦車です。キャタピラはプラスチックながら1つずつ連結していくもので、プラモデルの組み立て、塗装、ラジコン操作など様々なポイントから楽しむことができ、50年経った今でも鮮明に記憶に残っています。
この様なことを書いていると、ますます当時の記憶が蘇ってきます。無線とは全く関係ありませんが、Uコン飛行機に興味を向けたこともありました。
エンジンはビギナー向けのFUJI 099です。騒音対策としてサイレンサーを付けましたが、エンジン本体の両側に開いている四角い排気口に外側からバネの力で挟み込むもので、ENYAの丸っこいマフラー然としたものとは違い、子供心にデザイン性に難を感じたものです。とりあえず手作りの木製マウントにエンジンを固定してプロペラを付け、燃料タンクにグロー燃料を入れ、スロットルを少し開けて空回ししたのちグロープラグに2Vの小型鉛蓄電池をつなげて力を込めてプロペラを指で回してエンジンを始動する・・・などをやっていました。
飛行機本体も作ったのですが、実際にエンジンを搭載してワイヤを付けて飛ばした記憶がありません。模型屋でENYAのエンジンを眺めているうちにFUJIが見劣りし、徐々に興味が薄れていったのかも知れません。今でもFUJIやENYAのエンジンは売られているのでしょうか?