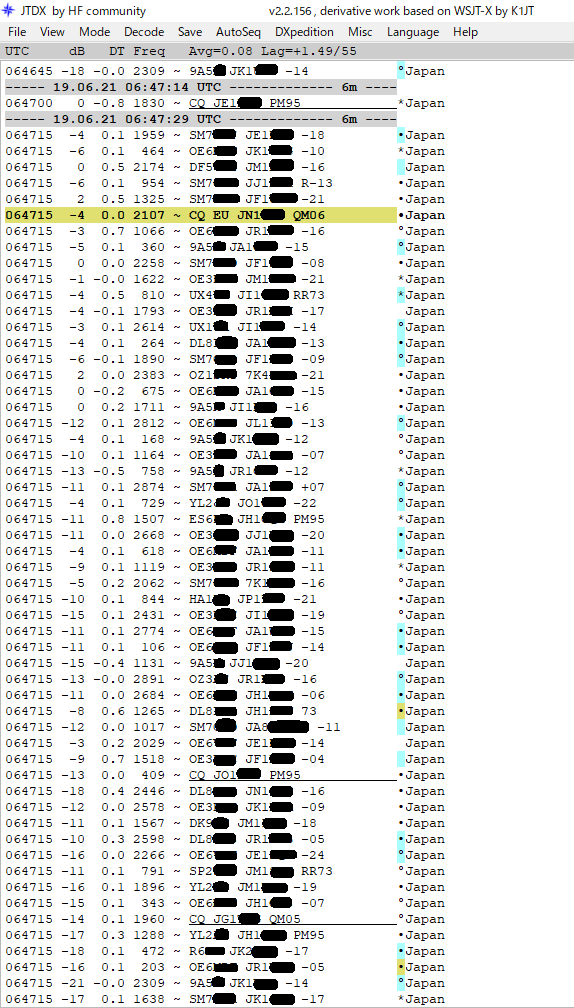大学では電波工学系の科目を割と多く履修していましたが、趣味と授業とでは全く違うことを感じていました。特に電磁気学は数式が数多く出てきてそれだけで頭痛がするくらいで、「電波」の基礎となる科目にもかかわらず全く頭に入って来ず、及第点すれすれだったと思います。
その他、空中線、電波伝搬なども理論の話になるととたんに理解不能に陥ったものです。おそらくそのような理論をきちんと理解できる人が、優れた研究者や設計者になれるのだと思います。
一方、私はというと結局「理論」についてはそれほど興味が湧くことがなく、今から思えばもったいない学生生活を送っていたと少し後悔しています。やはり難しい科目は授業を聴いているだけで理解するのは不可能で予習復習が必須なのですが、それをさぼったのがいけませんでした。何か消化不良というか中途半端な気持ちです。
今それを取り戻すのは不可能ですので、アマチュア無線の運用を通じて何か改善すべき課題があれば、なるべく原点に立ち返って調べることを心掛けています。ただ皆さんの改善ノウハウは、ネットやCQ誌を通じて大変役に立つことばかりですので、「理論」まで立ち返るような機会はほぼありません。
先日も、等方性アンテナと半波長ダイポールアンテナのゲイン差2.15(2.14)dBの意味を考えようと試みましたが、電力P(W)を放射するポイントからd(m)離れた場所の電力密度Sが、電力を球の表面積で割ったP/4πr2というところまではわかるとして、それと電界強度との関係さえ理解できず、その先の微小ダイポール、半端長ダイポールへの理解が進みませんでした。改めて電磁気学の難しさというか近寄り難さを感じます。
若い頃は「理解したつもり」「知ったつもり」の勘違いが多かったのだと思いますが、今となっては恥ずかしい限りです。