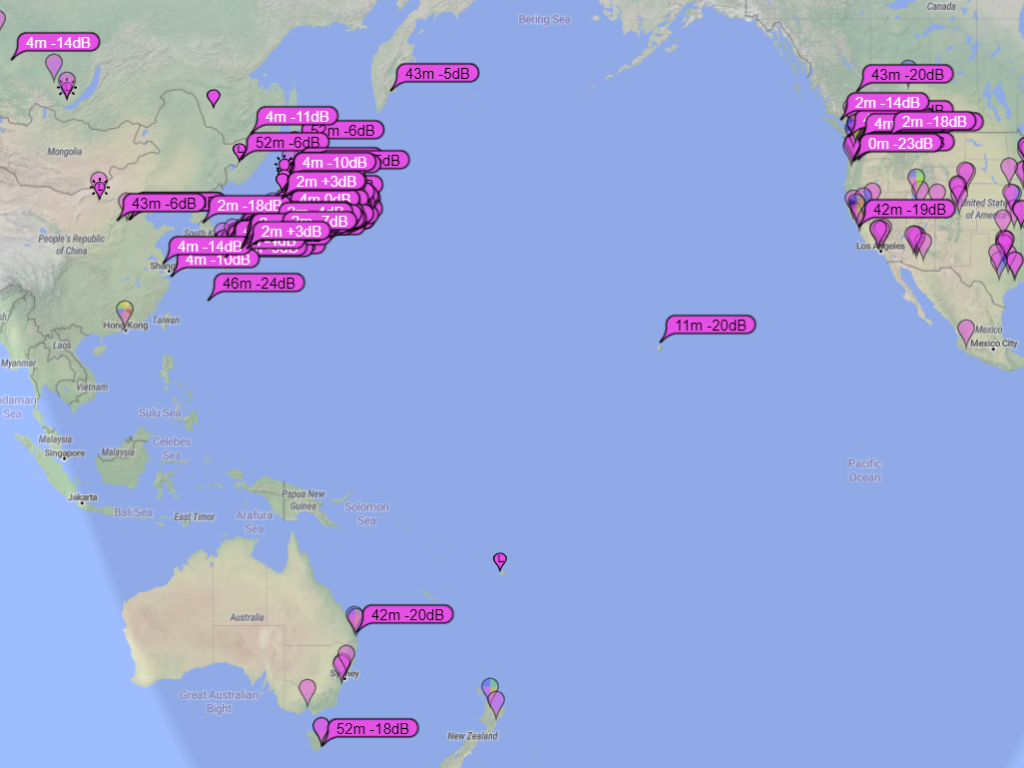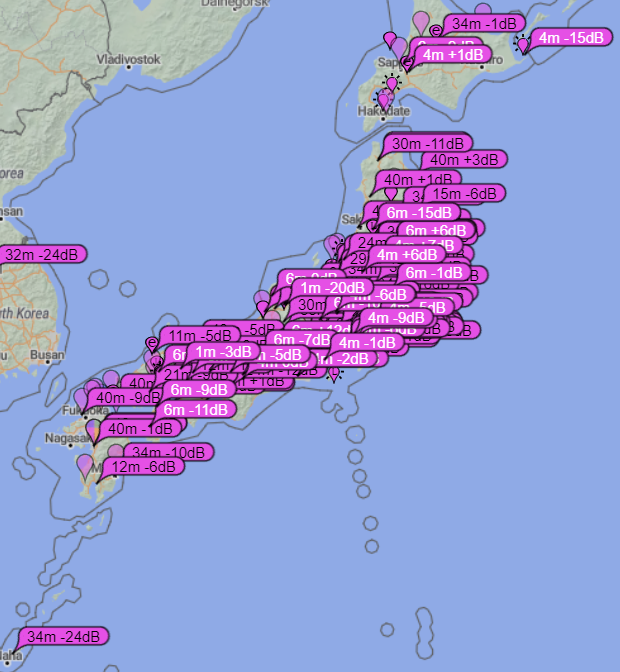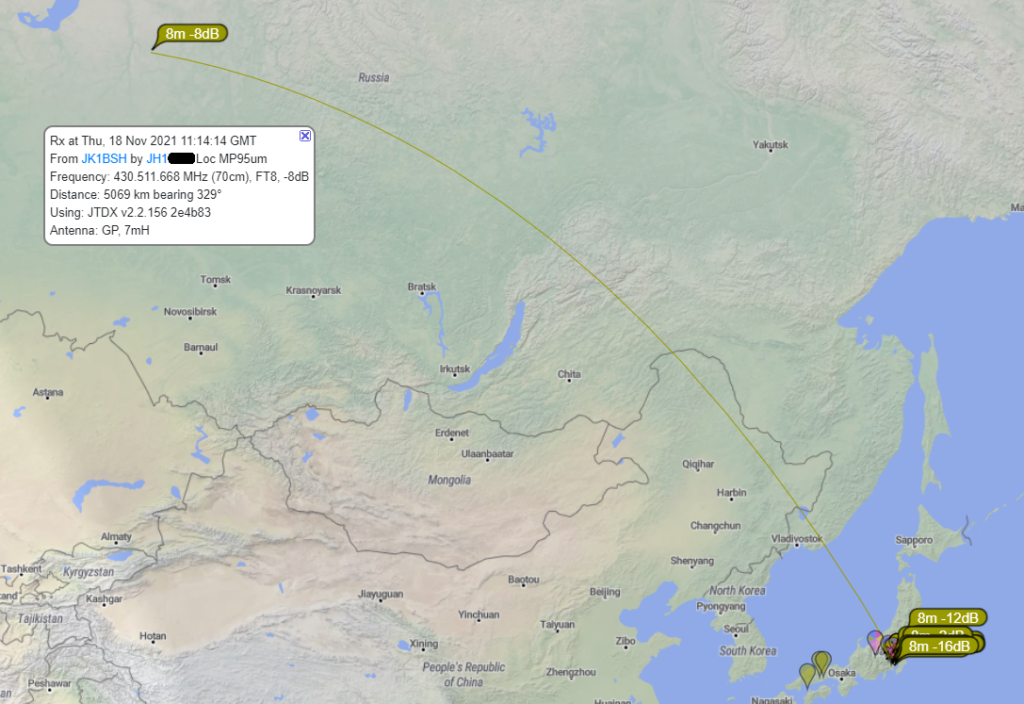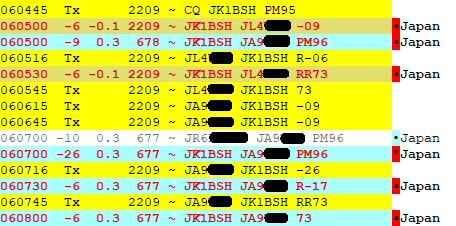この週末にベランダのアンテナ系を調えておきたいと思い、手持ちのモービル用ケーブルを活用することにして、それに合うようなクランプフィルタを入手しました。TDKの「ZCAT1518-0730」という3Dケーブル用のものです。
ちなみにCQオームさんの販売サイトを見ると、5D用クランプフィルタの「予約」表示は消えていましたので、既に状況は改善しているのかも知れません。ただ10D用は在庫切れの様です。
今回使用するモービル用ケーブルは、基台から出ている部分のケーブルが細いため、それを利用してこのように付けてみました。

フィルタ部分は二重に巻いています。また5Dケーブル部分はベランダ運用で邪魔にならないようにと、短くカットしMPコネクタを付けました。ここにNavoVNAをつないでアンテナ直下でSWRを測定することを想定しています。
この様に完成してみると、フィールドでの運用にも適していそうです。ひとまずベランダで試してみようかと思います。