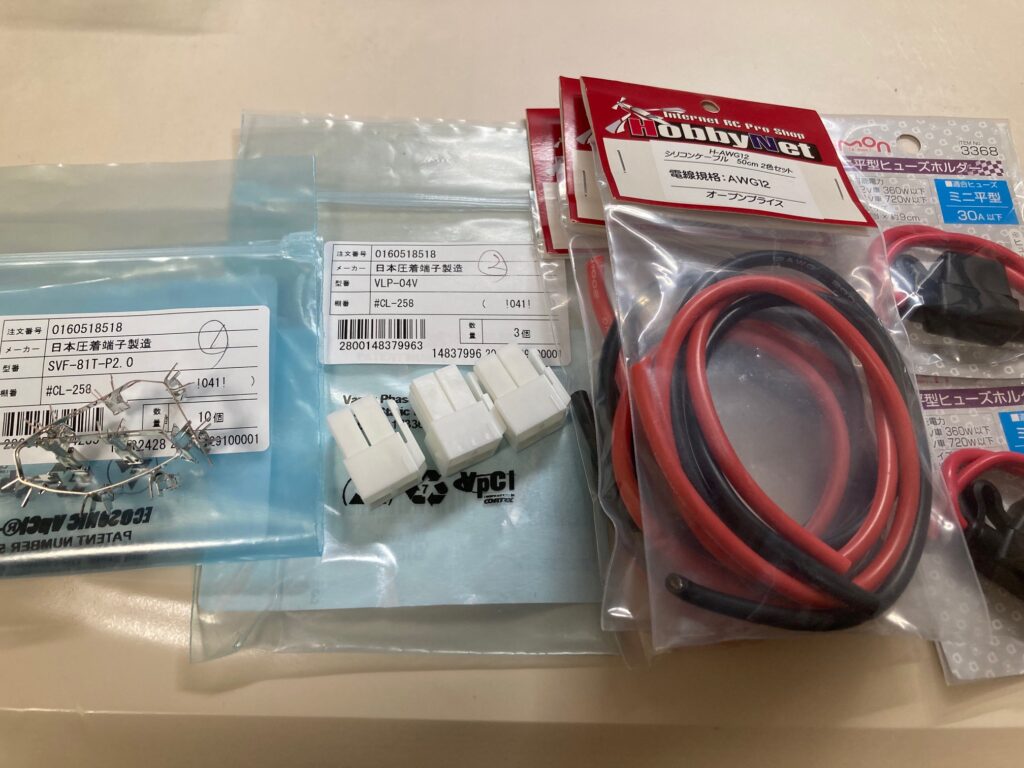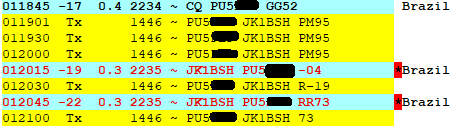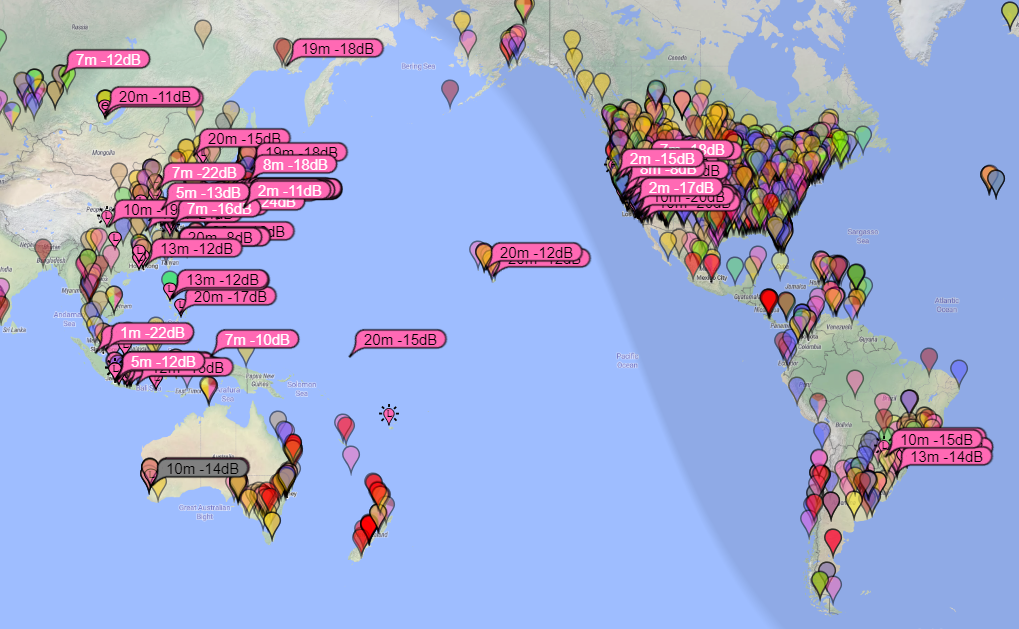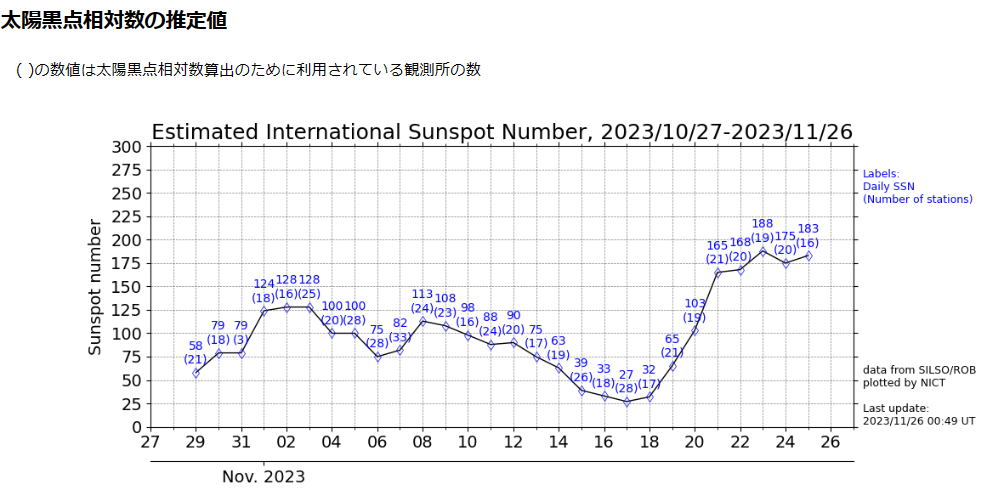この度、ハイモンドのMK-706を入手しました。これはCWエレキー用のパドルです。

このパドルはレバー間隔が狭いという特徴があり、使い勝手が良いかどうかはこれからのお楽しみとして、昔馴染みの「ハイモンド」製を使いたかったこともあってこれを選びました。モールドタイプとは別に大理石タイプも販売されていて少し迷いましたが、重量は何故かこちらのモールドタイプの方が重くしかも安価ということが決め手となりました。
何となくレトロ感が漂っていて懐かしさがあり、また通信機器っぽく落ち着いていて良い感じです。
若い頃はハイモンドの縦振り電鍵を使っていたのですが、中々綺麗に符号を打つことができず、速く打とうとすると文字がつながってしまったり、短点と長点のメリハリが付かず、それを意識して長点が長くなってしまったりした記憶があります。
それに手の疲労のことを考えると、この歳になってもう縦振りは無いかな・・・と思った次第です。要するに、今思えば縦振り電鍵の操作の基本をきちんと習得できていなかったのですね。
さてパドルの話に戻りますと、私は右利きですがパドルは左手で使うことにしてリグの方で短点・長点を反転設定しました。
実際にCWのQSOをワッチしてみると、今は皆さん打鍵速度がとても速いことに驚きます。コンテストではなく普通のQSOでも高速です。599BKであればコールサインさえ聞き取れれば何とかなるのかも知れませんが、昔ながらのラバースタンプや平文ではやはり不安です。
送信の方は、パドルでの練習を始めたものの、今のところ15WPMくらいが精一杯ですね。その速さでも短点の数がうまく決まらなかったり、一つの文字内で短点から長点に移るときに間が空いてしまったり、パドル特有の難しさを実感しているところです。
道路を走るクルマのように一人だけ速度が遅いと周りの方に迷惑になりそうですので、もう少し練習してから路上に出ようと思う反面、その時の自分のペースで受け入れて貰えるのではないかとも思います。まあ事故を起こす訳では無いので、それほど深刻に悩むこともないのですが・・・コミュニケーションの手段として、できるだけ綺麗な符号で正確に伝わることの方が重要と思っています。
ちなみにこれがカバーを被せた状態です。モールドの精度が良いのか構造的なものなのか、きっちりと嵌っています。