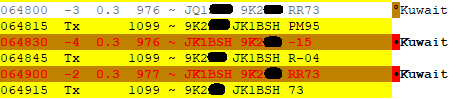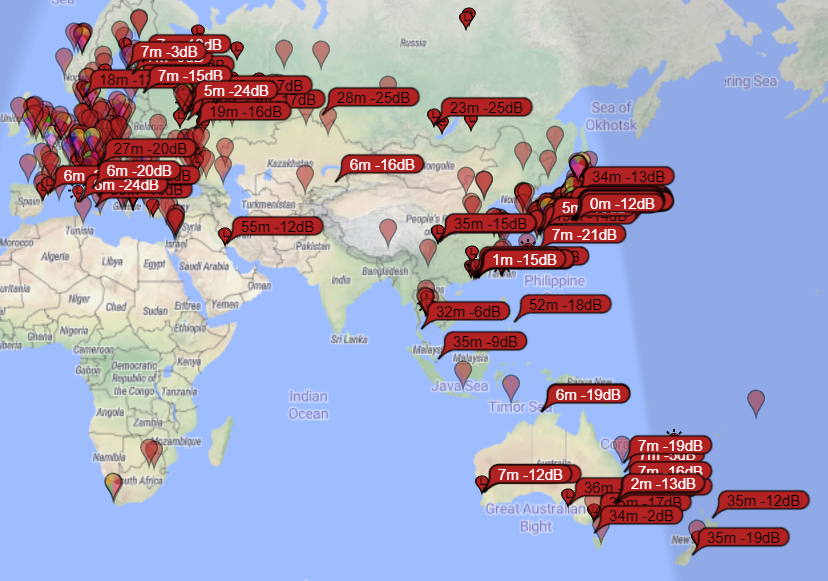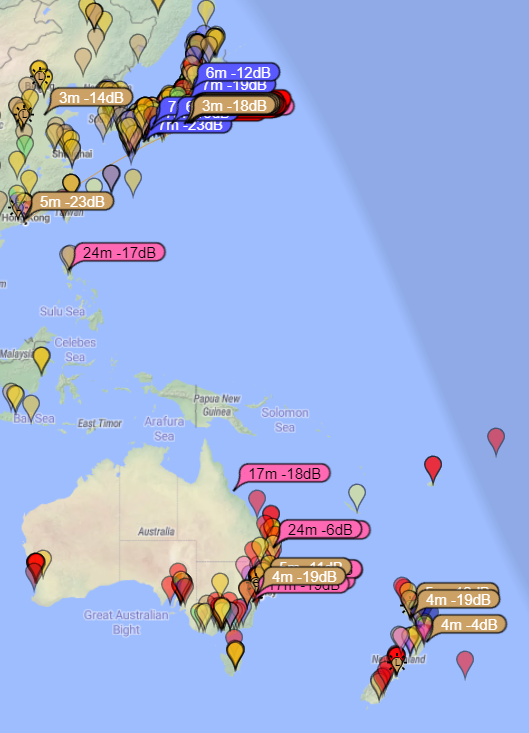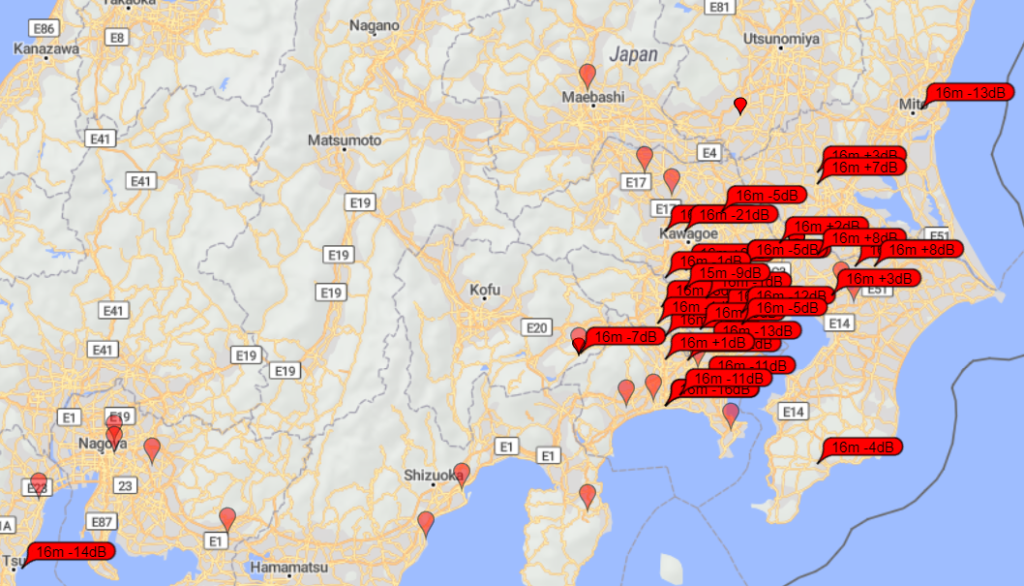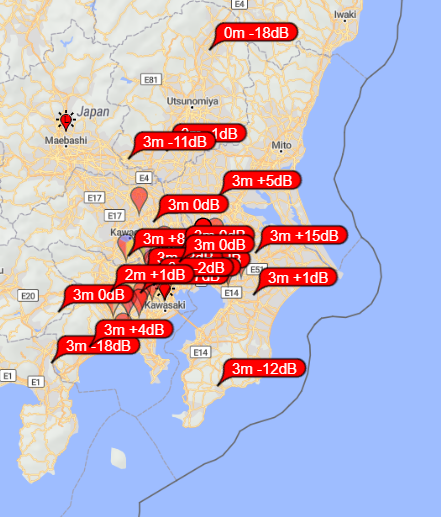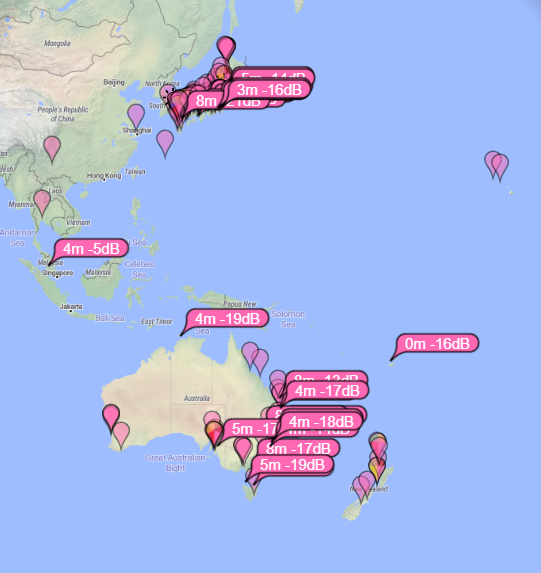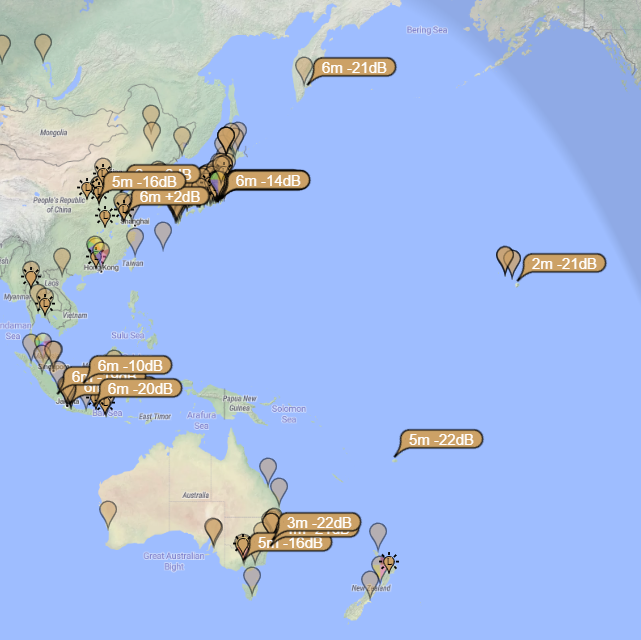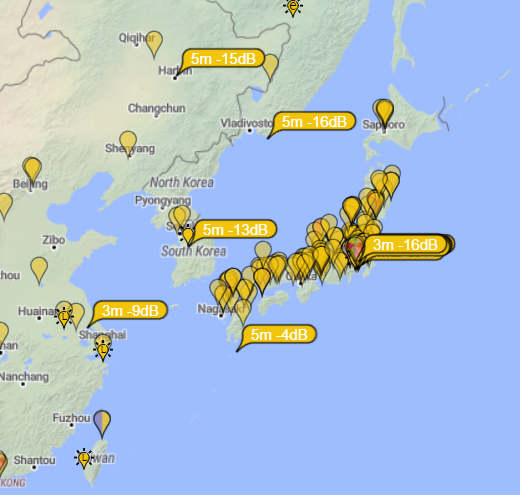今年に入ってからずっとATUのことが頭の片隅にあり、今回もまたその関係の話題です。
MFJ製の屋外型ATUは、同軸ケーブルに高周波信号と共に電源や制御信号を通すいわゆる「電源重畳」方式でコントロールケーブルが不要なのですが、そもそもこのようなアイディアはいつどこで生まれたのかを少し調べてみました。
とりあえず国内特許・実用新案を検索してみましたが電源重畳自体は昔からポピュラーな技術のようで、アンテナ制御関係に絞ってみたところ「実用新案登録第3034864号」がヒットしました。出願日は1996年8月19日、登録日は1996年12月11日です。特許と違って実用新案は簡易な審査なので出願から登録までが速いですね。請求項の内容は以下のとおりです。
【請求項1】
複数の周波数帯域を有し選択的に周波数を設定して無線通信を行う無線通信機において、選択した周波数に応じてアンテナの整合を行う整合部を備えたアンテナと無線通信機との間の送受信信号を通す同軸ケーブルに、送受信信号と整合部を制御する制御信号と整合部を作動させる電源とを重畳して通すことを特徴とする自動同調アンテナ。
【請求項2】
アンテナ整合部の同調コイルは、同調コイルに内接する導体の摺動子をモータ回転により摺動させてアンテナ同調させる構成とし、無線通信機とアンテナとを接続して送受信信号を通す同軸ケーブルに、モータ電源と、アンテナ同調のSWR信号に基づきアンテナ同調を行うモータの制御信号とを重畳させ、アンテナ整合部では、送受信信号はHPF、モータ電源はチョークコイル、制御信号はBPFにより各信号を分離してアンテナ自動同調をすることを特徴とする自動同調アンテナ。
このようにスクリュードライバアンテナ用の電源重畳に関する考案かと思いますが、請求項1は範囲が広く、ATUをアンテナの一部と解釈することもできそうですね。
ちなみにこれは八重洲無線から出願されたものです。ATAS-120などを想定したものでしょうか。すでに権利は失効しており、また他に特許があったとしても、この実用新案が先行技術となるため、少なくともこのようなコンセプトレベルでは特許について心配する必要はなさそうです。
あとは、実際に電源重畳を実現したり効率良くチューニングするための回路や制御手段、構造関係で特許が存在するのかが気になるところです。制御のアルゴリズムについてはノウハウ的な部分ですので、特許出願はされていないかも知れませんね。
今後、余裕があれば他社の特許なども調べてみたいと思います。