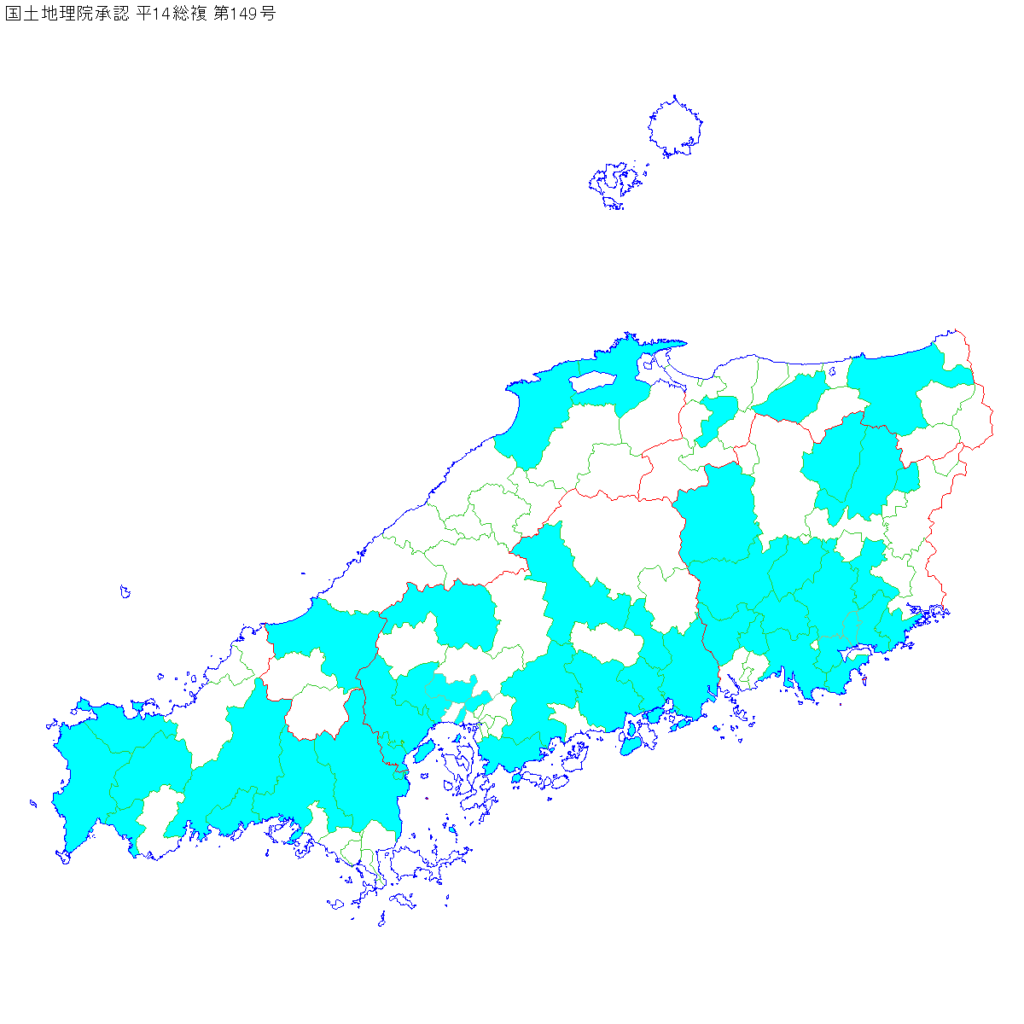2m/430用八木アンテナを、横出しブームを介さずに直接垂直の塩ビ製ポールに取り付けるためのクロスマウント金具を調達するため、以前購入したことのあるホームセンターに行ってみました。
しかし、所望の金具はすでに置いておらず、汎用のUボルトと金具を組み合わせて間に合わせようとしましたが、適当なものがありません。
当局のアンテナはベランダ内への取付のため、簡単で安価なTVアンテナ用の金具で十分なのですが、昔と比べてその様なTVアンテナ用の金具は種類が少なくなったように思います。仕方無く通販で注文しました。
ポールは今度ホームセンターに行ったときに調達しようと思います。